ヒトに寄生する蜂
汚いもの、弱いもの、劣るものを指して「虫」という言葉を使うことがある。
たしかに、個々の虫は小さく、知能が低く、か弱い存在であるように思える。しかしながら、虫には何億年という歴史を生き抜いてきた実績があり、それは虫の遺伝子に刻み込まれている。
人類は往々にしてヒトこそが最も進化した種だと考えがちだが、本作は長い地球史においてわずか 0.0004% の期間しか存在していない生物が、本当に「種」と呼べるのか、と問いかけている。

「アブラゼミが路上に落下し、起き上がることができず仰向けのままでいる」という事象に対して、本作では「自然界にはまっ平らな場所はないので、まだ適応していない」としながら、「長い歴史を有する虫にとっては、ヒトという生物が作った“まっ平らな場所”に適応する必要がない」という見解を示している。
では、もし明確にヒトを種として認め、標的とする虫がいたら? ――本作には、ヒトに社会寄生する「蜂」が登場する。二億年もの時間を生き抜いてきた蜂が人間社会を標的としたとき、一体どのように驚異となるのか。本作は、蜂が長い歴史の中で洗練させた〈蜂の常識〉が人間社会に注入されるという、 if の世界を描いたサスペンスである。
ヒトの常識 / 蜂の常識

本作の主人公である姫乃は、母親からもクラスメートからも「虫」と呼ばれ、いじめられている内気な女子高生だ。
だが、あるきっかけで「女王蜂」の力を身に着け、体からはスピアのような針が生える。この針に刺された女性は、女王である姫乃を守るために戦う忠実な「兵隊」となるのだ。それまで姫乃をいじめていた母親もクラスメートも、全員が姫乃を心から愛するようになり、全力で守ろうとする。
それは〈ヒトの常識〉からすると、まるで化物の能力であり、洗脳であり、気味が悪く、とても恐ろしいものであるように思える。実際に、作中では実在するカルト教団やテロ事件には「蜂」の関与があるという設定が登場する。ヒトの社会にとっては脅威なのだ。
しかし一方で、本作では「蜂」の能力や、その能力によって姫乃が為すこと、「兵隊」が姫乃を守るためにすることを、決して恐ろしいものとしては描かない。むしろ美しいものとして描いている。

姫乃に対してひどいいじめを行っていたクラスメートは、姫乃への愛を高らかに宣言するようになる。作中ではこの意思が偽りのものであるとは表現されない。それは純粋に、種が異なれば常識もまた異なるというだけのことである。
一方で、本作ではヒトの社会がいかにいびつであるかということも示している。ヒトは進化に失敗した。人間社会は脆弱である。そう主張している。
姫乃がいじめられっ子であるという設定は、この主張の重要な論拠となっているように思える。
自分より立場の弱い者を作り、なぶり、楽しむ。実の娘であっても愛することができない母親がいる。こんな社会を築いたヒトが、正しく進化した種であると誰が言えるだろうか。
姫乃は女王を中心として愛情と信頼で構築された楽園を望む。それはつまり、〈蜂の常識〉をもって統治される〈ヒトの社会〉である。つまり、〈ヒトの社会〉に対する〈蜂の常識〉の注入であり、〈ヒトの社会〉に対するアンチテーゼである。
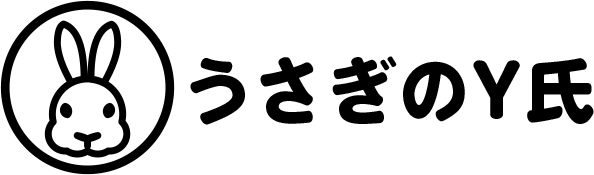 うさぎのY氏
うさぎのY氏
 mochieer
mochieer